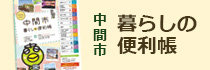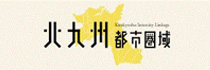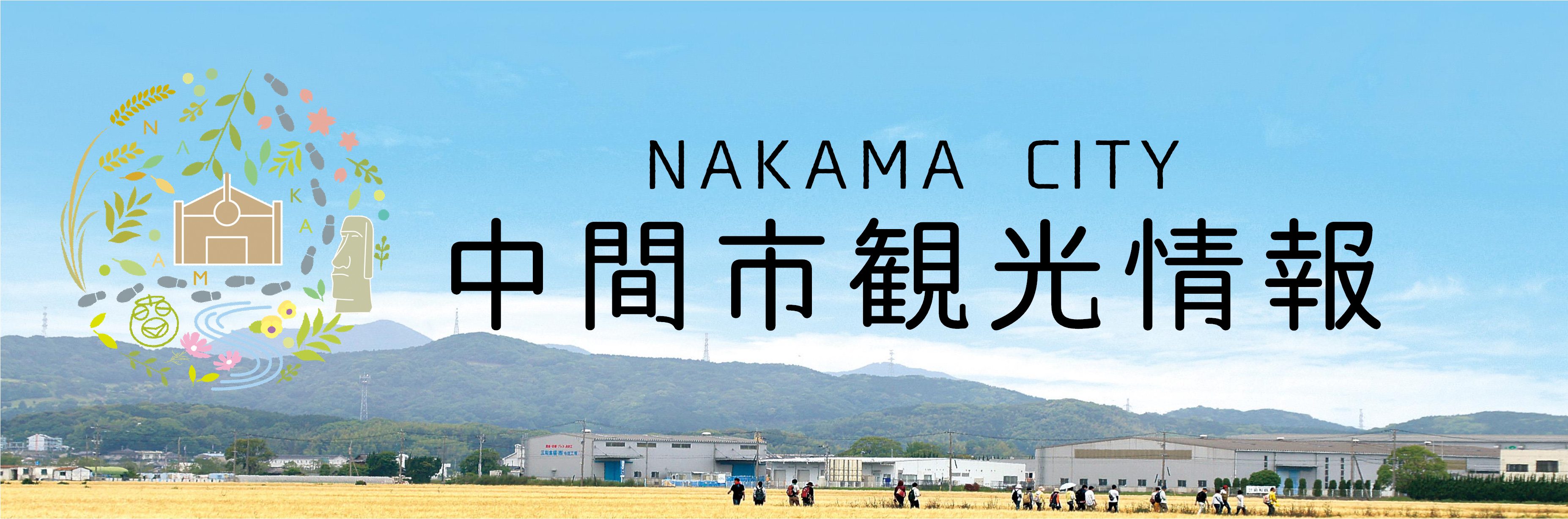| 議員名 |
質問事項・要旨 |
動画 |
| 柴 田 広 辞 |
1.コミュニティ広場の再編について
(1)福田市長が構想されている、コミュニティ広場の再開発構想について伺います。
(2)コミュニティ広場再編の進捗状況について、現時点でどのような検討・準備が行われているのかを伺います。
(3)今後のコミュニティ広場の再編事業に関するスケジュールはどのようになっているのか、基本構想の策定や市民参加の機会、委員会での審議・答申時期、最終的な事業化までの主なタイムラインを伺います。
(4)コミュニティ広場再編に関して、市民の意見聴取やパブリックコメントの実施予定等、市民のニーズを反映するための具体的な取組について、現段階の方針があれば伺います。
2.中鶴市営住宅の建替え後の跡地の活用について
(1)中鶴市営住宅の建替え事業の概要並びに現在の事業進捗状況を伺います。
(2)現在の中鶴市営住宅の入居率や空室数はどの程度かを伺います。
(3)建替えによる旧市営住宅の跡地について、具体的な活用案はどのようになっているのか伺います。
(4)今後の市営住宅事業について、現状の課題・方向性を伺います。(他の市営住宅事業への影響)
3.汚水処理場の跡地の活用について
(1)曙汚水処理場・中鶴汚水処理場の解体撤去にかかる工事は令和6年度までに実施されています。現在、解体後の土地の具体的な有効活用計画はどのように進んでいるのか、現状の進捗状況を伺います。
(2)双方の土地の活用に当たり、地域住民への説明や意見聴取等、コミュニケーションの取組状況について伺います。
(3)今後の具体的なスケジュール(着手時期や完了予定時期)と、土地活用に向けた今後の課題について、見解を伺います。
|
柴田広辞
質問動画<外部リンク> |
| 森 上 晋 平 |
1.中間市役所庁内のデジタル化推進とRPA導入による業務効率化について
RPAとは、「Robotic Process Automation」の略語で、ホワイトカラーのデスクワーク、主に定型作業をパソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代行、自動化する概念です。2042年には高齢者人口がピークとなり、自治体の税収や行政需要に極めて大きな影響を与えると考えられています。住民サービスの多くは地方自治体が支えており、スマート自治体への転換が求められています。その大きな動きの一環として、人工知能AIやRPAの導入が全国で活発化しています。総務省としてもこのようなテクノロジーの積極的導入を地方自治体に対して促しています。福岡県内におきましても、近隣自治体の古賀市の例を挙げれば、『多様な働き方ができる環境をつくり、職員のエネルギーをまちに還元する。』との理念に基づき、受付時間短縮を実現しました。職員同士の課題共有や議論の時間を増やし、政策立案機能の強化を図っています。このような取組は中間市にも参考になる点が多いのではないかと考えます。上記を踏まえ、以下の質問を行います。
(1)RPAの導入により、『介護保険資格の確認・介護保険料の算定』業務において、年間『業務時間81.5%の削減』を実現しており、RPAの利用をきっかけに、スマートシティやデジタル化に向けた職員の意識改革ができた例があるとのことです。中間市における定型業務のRPAの導入状況や計画について伺います。
(2)現状、RPAを導入していない、もしくは今後導入しない場合、窓口業務の遅延や職員の時間外労働が増加し、市民サービスの質が低下するリスクがあります。市はこのリスクをどう認識していますか。もしくはどのようにこのリスクに対応していこうと考えているのか伺います。
(3)高齢者向けデジタル支援と並行して、RPAの導入で職員の事務負担を軽減し、市民に向き合う時間を増やす計画及び福田市長の考えを伺います。
(4)RPA導入には業務フローの見直しや職員のスキル向上が課題とされています。本市におけるRPA運用を支えるデジタル人材の確保・育成についての考えを伺います。
2.ふるさと納税の増収策と地域振興の推進について
地域振興のためには、寄附金の効果的な活用と市民・事業者との連携強化が不可欠であり、今後の戦略を明確化する必要があると考えます。
ふるさと納税を活用した歳入確保と地域活性化に向けた具体的な施策を明確化し、持続可能なまちづくりを推進するため、以下の質問を行います。
(1)ふるさと納税の寄附額減少への対応策について
2024年の寄附額は2.46億円(全国888位)と前年比39.45%減でありますが、減少要因の分析と、2026年度以降の増収に向けた具体的な施策(例:新返礼品開発、SNS強化)について伺います。
(2)地域産品の返礼品強化について
総務省の地場産品基準強化後、返礼品の魅力向上が課題です。地元事業者との連携による新返礼品(例:遠賀川関連の体験型商品や地元農産物)の開発計画は進んでいるのか伺います。
(3)ふるさと納税寄附金はこれまで具体的にどのような事業実績があるか。また、今後の計画について伺います。
(4)企業版ふるさと納税の推進について
企業版ふるさと納税(例:2024年度の株式会社カームワ ークス等の寄附実績)を活用した地域プロジェクトの拡大策は何か。また、企業との連携強化策について伺います。
(5)市民参加型の地域振興策について
ふるさと納税を通じた地域振興において、市民や地元事業者の参画を促す仕組み(例:返礼品開発ワークショップ、市民向けPRイベント)の導入予定について伺います。
(6)これまでふるさと納税寄附額が低迷している原因の一つに委託会社のパフォーマンスの問題が考えられます。ふるさと納税寄附額の抜本的な向上の為にも、委託会社の再検討を行うべきだと考えますが、市の考えを伺います。
|
森上晋平
質問動画<外部リンク> |
|
阿部伊知雄
|
1.福田市長のこれから4年間の市政運営の抱負
福田市長は今回の市長選挙で多くの市民の信任を得て当選されました。しかし、他の市長候補にも多くの票が入りました。市民の分断と対立は市政の停滞を招きかねません。このような状況を踏まえ、福田市長は、これからの4年間どのような思いで市政運営をされるのか、市長のお考えをお聞かせください。
2.市の物価高騰対策について
ここ数年の物価高騰は、私たちの生活に大きな影を落としています。特に子育て世代や年金生活者の生活の厳しさは、想像を超えるものがあります。現在、国の物価高騰対策として、電気・ガス料金の補助等が行われていますが、これらの補助は9月末で終了する予定です。また、政府の備蓄米が放出されたにもかかわらず、まだまだ米の値段は高く、気候変動や国際情勢による様々な商品の価格上昇はこれからも続くことが予想されます。そこで、私は中間市として何らかの物価高騰対策が必要ではないかと考えます。
(1)このような近年の物価高騰による、市民生活がひっ迫する状況について、市はどのように感じていますか。
(2)中間市で水道料金の減免が実施できれば、国の電気・ガスの補助が終わった後の市民生活の支援が少しでもできるのではないかと思います。市はどうお考えでしょうか。
(3)市民生活の安定のために市内全世帯にお米券を配布してはいかがでしょうか。市の見解をお聞かせください。
3.市のプラスチックゴミ収集について
資源リサイクルや自然環境保護などの意識の向上、また、家庭における調理スタイルの変化により、家庭ゴミの中で、プラスチックゴミの量が増えていくのではないかと考えます。
(1)現在の生活系ゴミの分別方法や収集日のスケジュールは、いつ頃決めたものでしょうか。
(2)ゴミの分別方法や収集日のスケジュールを決めた頃のプラスチックゴミの収集量と、現在のプラスチックゴミの収集量の変化について伺います。
(3)プラスチックゴミの収集回数を増やすことについて、市の見解をお聞かせください。
|
阿部伊知雄
質問動画<外部リンク> |
| 植 本 種 實 |
1.福田市政3期目の中間市づくりについて
(1)市立病院を廃止しました。市民の中から「困っている」との声もありますが、このままで良いとお考えでしょうか。
(2)間借りと言われる生涯学習課、中央公民館などを今後どうされるのですか。「学びたい」と言う市民の声があります。
(3)学校施設のあり方について再度お尋ねします。今後の計画はどうなっていますか。
(4)コミュニティ広場の今後の計画について伺います。
2.ハピネスなかまについて
(1)令和4年度から令和6年度までの年間利用者数について
(2)利用者を増やすためにどのようなことをしていますか。
(3)バスの令和6年度の月ごとの利用者数について
(4)利用料金と令和6年度の決算総額について
(5)利用料と入館料の無料化について
|
植本種實
質問動画<外部リンク> |
| 迫 田 隆 太 |
1. 実感ある道徳教育の強化について
(1)小学校・中学校において道徳の授業は月にどれくらいの時間があるのか伺います。
(2)授業内容について机上教育(教科書・教材)が主なのか、それとも動画視聴等での実感ある道徳教育が主なのか伺います。
(3)全小・中学校、全学年において、過去に道徳を授業参観の科目として行ったことがどれくらいあったのか伺います。
2. 高齢者の孤独死防止対策について
(1)中間市における高齢者の孤独死の現状把握について伺います。
(2)中間市では高齢者の見守り体制をどのような活動で強化を行っているのか伺います。
(3)今後の孤独死防止対策の方向性について伺います。
|
迫田隆太
質問動画<外部リンク> |
| 原 舞 |
1.中間市老人クラブ連合会をはじめとする高齢者の活動について
中間市は高齢化率が38.2%と国や県を大きく上回っており、高齢化に伴う地域課題への対策として介護予防や認知症予防の取組が行われています。なかでも老人クラブや各自治会の老人部、老人会等を中心とする住民主体の活動は、介護予防や認知症予防に大きな成果となっています。しかしながら役員、運営側の会員も高齢化し、各団体の運営や活動に支障が生じているのが現状です。
(1)福田市長は中間市老人クラブ連合会や各地区の自治会における高齢者の活動内容をご存じですか。また参加されたことがあるのか伺います。
(2)その活動に対する行政からの補助があるのか伺います。
(3)役員の高齢化で運営が困難になっている中間市老人クラブ連合会の運営に対する行政の支援体制について伺います。
2. 障がいのある人の介護予防、社会参加について
ノーマライゼーション、心のバリアフリー、合理的配慮の提供等、障がいのある人への理解を進めるワードは、以前に比べ目にする機会が増えましたが、本市では、障がいのある人への理解促進は実現できているのでしょうか。
(1)障がいのある人が社会参加する意義、もたらす効果について市の見解を伺います。
(2)視覚障がいや、聴覚障がいのある人への介護予防等の情報提供の方法について伺います。
3. 要保護児童対策について
『すべてのこどもが夢や希望をもち笑顔あふれるまちなかま~だれひとり取り残さない!「こどもまんなか」社会をめざして~』この目標と共に今年3月に中間市こども計画が掲げられました。また放課後等デイサービスも拡充され、支援が必要な子どもたちに、よりこまやかな支援が届くよう環境も変化しつつありますが、支援の連携について、そのような体制が構築されているかを伺います。
(1)障がいのある人が社会参加する意義、もたらす効果について市の見解を伺います。
(2)視覚障がいや、聴覚障がいのある人への介護予防等の情報提供の方法について伺います。
|
原舞
質問動画<外部リンク> |
| 大 和 永 治 |
1. 投票率の増加に向けた取組について
(1)投票率増加に向けて、啓発・教育活動について伺います。
(2)投票率増加に向けて、投票環境の利便性について伺います。
(3)投票率増加に向けて、地域・市民との連携について伺います。
(4)投票率増加に向けて、新しい技術の活用について伺います。
(5)投票率増加に向けて、これまで中間市が行ってきた取組の成果について伺います。 |
大和永治
質問動画<外部リンク> |
| 掛田るみ子 |
1. 5歳児健診と健診後の支援について
今年度から、5歳児健診が始まり、子どもの発達支援の充実が図られるものと期待しています。5歳児健診の目的と健診の状況、健診を受けた後の支援などについて伺います。
(1)5歳児健診の目的と内容について
(2)健診の状況について
(3)健診後の支援はどのように行われるのか
2. 野良猫対策について
昨年11月「中間市ワンヘルス推進宣言」を行い、本年3月広報なかまでは、「猫と人の共生を目指して」と題し、地域猫活動の進め方が紹介されました。地域猫活動の現状と課題、野良猫の数を減らすためのTNRについて伺います。
(1)地域猫活動の申請状況について
(2)地域猫活動の申請要綱について
(3)地域猫活動の予算について
(4)環境保全のためのTNR費用の在り方について
|
掛田るみ子
質問動画<外部リンク> |
| 田 口 澄 雄 |
1. 学校給食費の無償化について
校給食費の無償化については、近隣自治体でも進んでいますし、来年度からは、国も動き出すようです。また、1期目の市長公約でもありますので、小中学校の完全給食無償化を早急に実施することについて、市長の見解を伺います。
2. 加齢性難聴者のための補聴器購入に係る市独自の助成制度について
昨年度の9月議会で公明党議員からも質問があり、窓口への対応と新たな購入助成制度を求める意見がありました。前向きに検討するという答弁でしたが、その後の進展を伺います。
3. エアコンの購入助成について
異常気象で、長期にわたる猛暑がくり返されています。こうした中で、エアコンの未設置の世帯や、故障して新たな購入が求められる世帯では、もはや我慢の限界を超えた状況が起こっています。こうしたことから、東京都足立区などでは、障がい者世帯や低所得世帯に対する購入補助制度を行っています。市民の命と暮らしを守るのは、自治体の重要な責務です。エアコン購入補助制度の実施について、市の見解を求めます。
|
田口澄雄
一般質問<外部リンク> |
| 原 口 佳 三 |
1. 中間市の学童保育の実態について
学童保育は、子供の健全な育成、保護者の子育てと仕事の両立支援、生活の安定、学習習慣の定着、安全・安心な環境の提供、異年齢交流の促進、地域との連携などを目的とされています。
(1)中間市の学童保育の実態を伺います。
(2)保護者の方は仕事が終わってもすぐには帰れず、残業になる事もあります。そんなときに、延長して預かることが出来るようにならないのか伺います。
(3)現在、学童保育を利用しているのは4年生までの児童が主と伺っていますが、6年生まで預かることは可能なのか伺います。
2.住宅地の庭木について
住宅地の庭木が大きく成長し近隣に迷惑をかけている状況が見受けられます。考えられるのは、空き家で手入れがされていない、高齢で自分で出来なくなったなどが考えられます。
(1)中間市はこの状況を把握し、対策を考えているか伺います。
(2)庭木が電線に当たっているのを見たことがありますが、危険性はないのか伺います。
|
原口佳三
質問動画<外部リンク> |