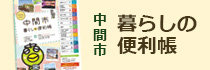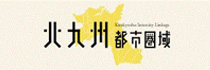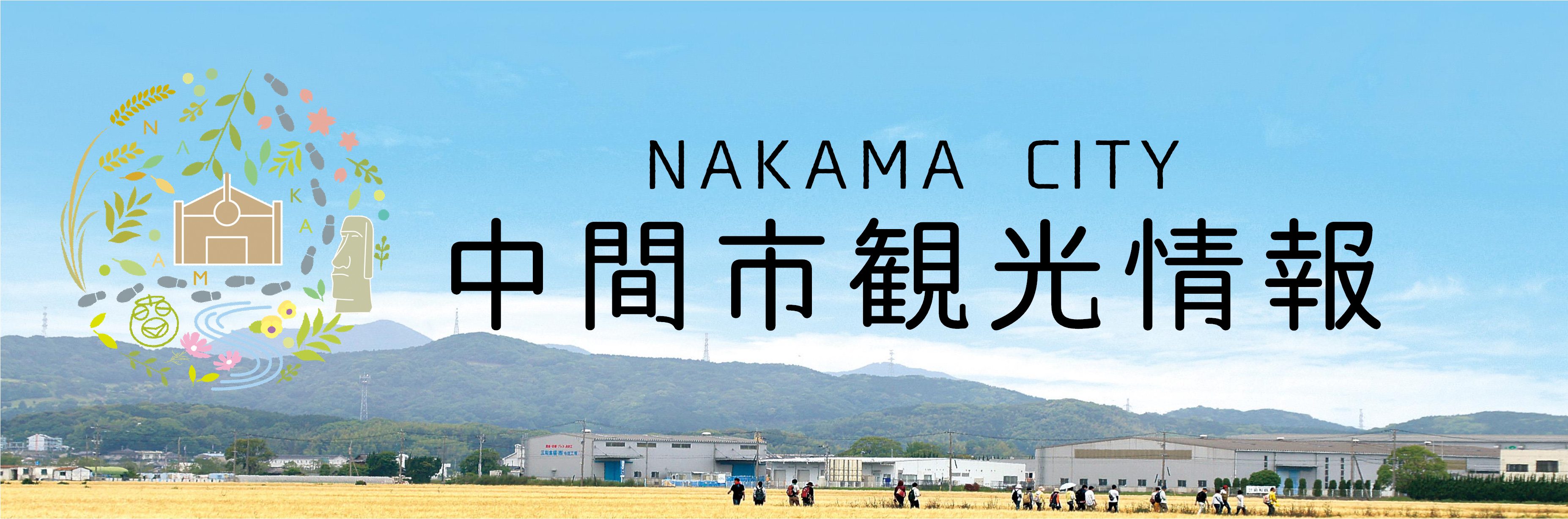| 議員名 |
質問事項・要旨 |
動画 |
| 森 上 晋 平 |
1.高市内閣総理大臣の所信表明演説を踏まえ、中間市がどのように政策的連携を進めていくかについて
高市早苗内閣総理大臣が本年10月24日に行われた第219回国会における所信表明演説において、強い経済の実現、物価高対策の推進、社会保障改革、防衛力強化などを重点政策として掲げられました。これらの政策は、我が中間市にとっても無縁ではございません。特に、物価高対策や社会保障改革は、市内の生活者支援に直結し、防衛力強化は地域の安全保障環境の向上に寄与するものと考えます。
つきましては、所信表明演説の関連性の強い箇所について、高市内閣総理大臣の問題意識を踏まえつつ、高市内閣と中間市がどのように政策的連携を進めていくか、市の見解を詳細に伺います。
まずは所信表明演説から中間市との関連性が高い箇所について、市の見解を求めます。
(1)物価高対策と「責任ある積極財政」の推進について
暮らしの不安を希望に変えるための基盤として、戦略的な財政出動を約束する内容の演説を受けて本市はどのように国、地方の政策的連携を図っていくか詳細を伺います。
(2)社会保障改革と「国民会議」の新設について
高齢化社会での持続可能性を強調し、維新の社会保険料引下げに配慮した柔軟な改革を示唆しています。この演説を受けて本市はどのように国、地方の政策的連携を図っていくか詳細を伺います。
(3)防衛力・経済安保強化と地方投資について
経済安保を「危機管理投資」と位置づけ、地方の安全保障を経済成長に結びつけると述べています。この演説を受けて本市はどのように国、地方の政策的連携を図っていくか詳細を伺います。
(4)全体的な共同推進の枠組みについて
高市内閣の少数与党状況を踏まえ、演説で「政権の基本方針と矛盾しない限り、各党からの政策提案をお受けし、柔軟に真摯に議論する」との柔軟性が、中間市との共同を後押しすると考えます。
ア 財源確保について
積極財政の交付税増額(推定50億円規模)を、教育・産業投資に優先配分、維新の政策(社会保険料引下げ、副首都構想)と融合し、福岡北部圏の成長モデル構築を図ることについて市の見解を求めます。
イ モニタリングと評価について
今後の政策の共同推進について、成功指標として、例えば、人口増加率1%、財政健全化率向上を設定するなど、2026年末までに共同成果報告書を作成し、モニタリングと評価を行うことについて市の見解を求めます。
(5)副首都構想について(バックアップ機能も含めて)
高市政権発足後、副首都構想の文脈で、北九州地域全体でのバックアップ適性が強調されています。いわゆる北九州市の『バックアップ都市構想』に本市がどのように関わっていこうとしているか、本市の見解を伺います。
2.本市の雑草に関する抜本的な対策について
中間市では、主に空き地(あき地)や農地、道路脇などで雑草の繁茂が問題となっており、市民の生活環境や景観に影響を及ぼしています。市はこれを防ぐため、条例を設けて空き地の管理者に適正な除草を義務付けています。
中間市第3次環境計画を見ても、市には毎年、草木に関する苦情が多く寄せられており、また、市民アンケート調査の結果、管理されていない空き家が多くなっているとの意見が寄せられました。
(1)市民からの相談件数は安定傾向ながら、放置空き地の増加により、雑草の目立つ箇所が残存しており、害虫発生や不法投棄のリスクが指摘されています。民法改正により、隣地への越境枝葉の自己切除が可能になったものの、空き地管理の抜本解決には至っていません。あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例の現状と民法改正によってどのような効果を得ることができたか市の見解を伺います。
(2)現状を踏まえれば、現行のあき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例の限界は明らかであると思います。うつくしいまちづくりのために条例に下記の改正を加えることについて市の見解を伺います。
ア 罰則の強化と執行プロセスの明確について
現状では現在の過料は抑止力に欠け、指導から執行までの期間が長く、雑草の即時除去が難しいと考えます。罰則の強化と執行プロセスの明確化が必要だと考えますが、本市の見解を伺います。
イ 条例の適用範囲を『対象を「空き地等」から「空き地、未利用農地、公共道路隣接地」に拡大』することについて
現状は主に空き地対象で、道路脇や農地境界の雑草が条例外となり、全体的な景観悪化を招いていることから、対象を「空き地等」から「空き地、未利用農地、公共道路隣接地」に拡大し、高さ基準を50cmから30cmに引き下げ、繁茂定義に「害虫発生リスク」を追加することについて本市の見解を伺います。
ウ 現状として所有者の経済・労力負担が大きく、特に高齢者や遠方所有者が対応しにくいことから、雑草対策の支援やインセンティブを付けることが必要であると考えます。具体的には、低所得者向け補助金制度として、例えば草刈り業者委託費の半額補助や防草シート設置補助を行うこと、また、インセンティブとして、例えば、定期管理証明書発行で固定資産税減免や空き地活用促進(貸出等)で税優遇を行うなどの雑草対策について、市の見解を伺います。
|
森上晋平
質問動画<外部リンク> |
| 大 村 秀 三 |
1.地域特性に応じた中間市独自の移動手段の確立について
(1)「デマンド型乗合交通」の導入について
スマートフォンや電話で予約すると、地域内を小型車両が回り、必要な時に駅や病院、商業施設まで乗り合いで送迎する仕組みです。
太賀・通谷などの坂道や狭隘道路にも対応しやすく、また、底井野のような集落地域でも柔軟に運行できるため、既存のタクシー事業者と連携することで実現可能です。
太賀・通谷・川西といった地域特性に応じて、小型モビリティ等を利用したデマンド型乗合サービスの導入を検討する考えはあるのか伺います。
(2)「筑豊電鉄との連携強化」について
中間市は既に鉄道事業者に対して安全性向上設備の整備費補助を行っており、鉄道を守る仕組みはできています。
今後は、鉄道駅を中心にコミュニティバスやデマンド交通を接続させ、『駅まで乗せる小さな交通+鉄道で都市圏へ』という交通ネットワークを整備すべきです。
筑豊電鉄を軸とした「駅+地域交通」のネットワーク化を、今後の中間市地域公共交通計画にどう位置づけるのか伺います。
(3)「市民参加による交通利用促進の仕組みづくり」について
地域で守る交通という理念のもと、各校区や自治会での利用促進キャンペーン・乗合サービスへのポイント給付など、市民が使いやすくなる工夫を取り入れることも重要です。
現在のコミュニティバスや路線バスの赤字を踏まえ、より効率的で持続可能な「中間市独自の交通モデル」の実証実験を行う考えはないか伺います。
2.若い世代、特に女性が働きやすい環境づくりについて
(1)女性が働きやすい職場環境の整備について
育児や介護と両立できるような柔軟な働き方として、例えば在宅勤務などを市として導入・支援することについて伺います。
(2)市内事業者への支援について
女性が働きやすい職場づくりに取り組む市内の企業や店舗に対して、支援や助成を行う考えはあるのか伺います。
(3)飲食・サービス業など地域密着型業種への支援について
例えば、私がSNSで取り上げた飲食店など、地域に根ざした職場では女性が活躍していました。
市として、こうした職場で安心して働き続けられるよう、人材育成や店舗同士の連携支援などを後押ししていただけないか伺います。
(4)関係人口の拡大と女性の活躍の連携について
私もSNSで中間市の魅力を発信し、関係人口の拡大に取り組んでおります。
この流れを活かし、地域で働く女性の活躍とつなげることができればと思います。
市外から関わる若者や女性が、将来的に中間市で働き、暮らすきっかけになるようなプロジェクトを、市として検討していただけないか伺います。
|
大村秀三
質問動画<外部リンク> |
|
阿部伊知雄
|
1.市内の空き家の現状とその活用について
中間市は、いよいよ中央公民館が解体され、コミュニティ広場の開発計画が進行しています。しかし、よくよく中間市全体を見ると、住宅地の中には空き家が多く見受けられます。空き家対策は、周辺住民への防犯や衛生、台風などの災害を考えたとき、中間市においても重要な課題であると思います。そこで伺います。
(1)現在市内にある空き家の件数(実態)を伺います。
(2)「空き家対策特別措置法改正」により、中間市の管理不全空き家の状況に変化はありますか。もしあれば教えてください。
(3)市内の空き家を現在どのように活用しているのか、伺います。
(4)中間市内在住の方が中間市の空き家を購入するときの市の補助金制度について伺います。
(5)親が市内に住んでいて、その子どもや孫が市内の空き家を購入する時などに特別に中間市が補助金を出すなど、何かしらの制度を考えてはどうでしょうか。空き家を活用して若年世代を増やすことにもつながると思います。市の見解を伺います。
2.市内の文化活動グループやサークルへの支援について
文化は世代の違い、男女の違い、民族の違いを越えて人々を結ぶ力があります。11月1日から3日にかけてハーモニーホールで行われた市民文化祭のステージでは、歌、ダンス、舞踊、民謡、楽器演奏、ファッションショーが行われていました。ロビーでは、俳句に短歌、川柳、華道に書道にペン習字、絵画、写真、陶芸など独創的な作品が多数出展されていました。別室では茶道でお茶も点てられていたと伺いました。会場では、若い世代の方も高齢の方も生き生きと活動されていました。そこで伺います。
(1)現在、市に登録されている文化活動を行うグループやサークルの数はどれくらいあるのでしょうか。
(2)それぞれのグループやサークルの活動場所についてはどのようになっているのでしょうか。
(3)それぞれのグループやサークルの活動に対して、市からの補助金などはあるのでしょうか。
(4)市民の心を豊かにし、市の活性化をはかるためにも、市民の文化活動、生涯学習活動がしやすい環境を整えることが必要だと思います。市の見解を伺います。
|
阿部伊知雄
質問動画<外部リンク> |
| 大 和 永 治 |
1.子育て支援の充実について
(1)子育て支援施設の充実について
ア 現在の保育所・認定こども園の待機児童数はどのような状況ですか。
イ 民間事業者や地域と連携した保育の受け皿拡大の方針はありますか。
ウ 子育て支援センターなど、親子の交流の場を増やす計画はありますか。
(2)経済的支援について
ア 子ども医療費の通院・入院の自己負担額を完全無償化する等検討されていますか。
イ 第三子以降の保育料や給食費の無償化など、負担軽減策は検討されていますか。
ウ 出産・育児に関する給付金や応援金制度の見直し予定はありますか。
(3)働く親への支援について
ア 在宅勤務やフレックスタイム導入など、市職員自身の働き方改革の取組は行っていますか。
イ 子育て世代が地域に戻りやすい環境づくりのための在宅支援や移住促進策はありますか。
(4)学校再編に関わる子育て世代への情報の共有について
ア 中学生未満の子どもがいる子育て世代へ重点的に情報発信はされていますか。
イ 子どもを保育所やこども園に預けている親へのアンケートや聞き込みなど検討されていますか。
|
大和永治
質問動画<外部リンク>
|
| 原 口 佳 三 |
1. 高齢者で低所得者の住宅支援について
今、中間市は高齢化率が約38%と、全国平均よりも高い水準を示しております。その中で高齢者の独居の方も増え、今後、安心して生活していけるのかという問題が出てきます。そこで伺います。
(1)75歳以上の独居の方の人数について伺います。
(2)そのうち身寄りの居ない方の人数について伺います。
(3)高齢で低所得の方に配慮した住居が市内に今あるのか伺います。
(4)今後、高齢で低所得の方が住める住居や施設などの建設予定があるのか伺います。
2. 介護施設や介護従事者について
市内の介護施設の方に話を伺うと、高齢者施設の運営が厳しい、介護スタッフが足りていなくて、なかなか入って来ない。そのため、外国人労働者を雇っているが、逆に経費が掛かってしまうという声がありました。また、以前から言われている、大変な仕事の割には賃金が安いということがあります。そこで伺います。
(1)市内の介護施設の経営状況について現状を伺います。
(2)市内の介護従事者の賃金における国・県の処遇改善に関する施策について、市として周知・支援を行っているのか伺います。
(3)外国人労働者を雇用する際に、施設に対して市から何かしらの援助はあるのか伺います。
|
原口佳三
質問動画<外部リンク> |
| 堀 田 克 也 |
1.自治会加入者の減少に対する取組について
近年、本市においても自治会への加入率が年々低下傾向にあります。自治会は防災・防犯・環境美化・地域行事など住民同士のつながりを支える重要な組織であり、地域の絆を守る基盤とも言えます。しかし、少子高齢化の進行や働き方の多様化、更には転入してくる世帯の地域への関わり方の変化などにより、従来の自治会活動の形が合わなくなっている現状もあります。こうした中で、校区まちづくり協議会が地域コミュニティの中核的な存在として期待されています。自治会加入者の減少に対する取組に係る次の項目について伺います。
(1)世帯数及び自治会加入率の推移について
(2)加入率低下の主な要因の分析について
(3)分析してからの加入率を上げる対応について
(4)特に若い世代や転入世帯への加入促進施策について
(5)自治会連合会の役割の現状について
2. 校区まちづくり協議会の運営について
本市は小学校区ごとに校区まちづくり協議会を設置しています。6小学校ありますことから6つの校区まちづくり協議会がありますが、この校区まちづくり協議会について伺います。
(1)設置された時期及び目的について
(2)校区まちづくり協議会の設置場所について
(3)参加されている自治会及び組織している構成員について
(4)各校区まちづくり協議会の事業内容について
(5)校区まちづくり協議会の取組内容と実績の評価について
(6)効果がある事業と形骸化している事業の見極めについて
(7)各協議会の交流や合同での会議について
(8)校区まちづくり協議会への支援体制(金銭的、人的)について
(9)役員、運営委員、および事務局員の報酬について
(10)高齢者主体の運営になっていることについて
(11)今後の校区まちづくり協議会のあり方について
|
堀田克也
質問動画<外部リンク> |
| 原 舞 |
1.青少年育成について
中間市こども計画では基本目標である「若者と未来~若者の生活を支え希望に応じた未来」を支援するための具体的施策として「青少年の非行防止と有害環境の浄化」や「青少年健全育成に対する市民意識の高揚」などが挙げられています。
(1)それぞれの活動の中心的存在である中間市青少年育成市民会議及び中間市青少年問題協議会の役割、また、活動内容を伺います。
(2)今後の中間市青少年育成市民会議との連携、また、支援の方針について伺います。
2.高齢者の介護予防事業について
一般介護予防事業であるケアトランポリンわいわい教室の終了後、通いの場を失った参加者からは不安を訴える声が多く寄せられました。また後期高齢者が増加する中で介護予防の機会が失われたことは、本市の地域包括ケアシステムの構築において大きな損失になっています。
(1)ケアトランポリンわいわい教室の代替となる介護予防事業の展開および進捗状況について伺います。
(2)一般介護事業を含む市民向け出前講座の実績を伺います。
(3)職員におけるアウトリーチの必要性について市の見解を伺います。
|
原舞
質問動画<外部リンク> |
| 掛田るみ子 |
1. 物価高騰に対する支援について
新政権が誕生し、初めての総合経済対策では、物価高騰対策として、地方自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」の拡充が盛り込まれました。
「推奨事業メニュー」にはプレミアム商品券、マイナポイントの発行などに加え、「お米券」も加えられたそうです。
中間市民の生活を支えるための経済支援策についての所見を伺います。
2. 動物虐待と治安の維持について
今年になり、垣生公園で、猫の変死体が見つかっていると情報が届きました。市はどこまで把握し、どの様な対応をしてきたのか、また、情報共有のあり方及び治安維持のための今後の対策について伺います。
(1)猫の変死体の発見状況とその対応について
(2)情報共有の必要性について
(3)防犯カメラの設置など、治安維持のための対策について
3. 民生委員の現状と今後のあり方について
民生委員は、自治会で選出していますが、自治会長の負担になっていると伺いました。人選ができず民生委員が不在の自治会もあるそうですが、その状況と今後のあり方について伺います。
(1)民生委員の役割について
(2)民生委員の選出のあり方について
(3)民生委員不在地域の状況について
(4)社会福祉協議会と民生委員の関係について
(5)今後の対策について
|
掛田るみ子
質問動画<外部リンク>
|
| 田 口 澄 雄 |
1. 学校給食費の無償化について
(1)学校給食費の無償化については、本年10月から実施されましたが、その財源には国庫支出金と一般財源があります。
もし、国の臨時交付金が無くなった場合はどうなりますか。
2. エアコンの購入助成について
(1)障がい者世帯や低所得者世帯に対するエアコン購入助成制度については、本年9月議会では検討するとのことでしたが、エアコンには、「2027年問題」といわれる、省エネ基準の厳格化などにより現在販売されている低価格のエアコンの多くが2027年度から販売されなくなる恐れがあります。
来年の夏に向けて、早急に助成制度の整備が必要だと思いますが、早急に本制度をスタートさせることについて、市の見解を伺います。
3. 水道料金の改定の問題について
(1)水道事業の赤字化と、今後の施設の維持・整備に多額の費用を要することから、早晩値上げが検討されると聞き及んでいますが、昨今の物価高騰の中で、市民生活は疲弊しています。
市民に負担を転嫁することなく、施設については一般会計からの出資金で、赤字については繰入金で補填し、なるべく市民負担の軽減に努めるべきではないでしょうか。
(2)また、料金改定については、そうした努力の後に、時機を見て検討すべきではないでしょうか。市の見解を伺います。
|
田口澄雄
質問動画<外部リンク> |
| 植 本 種 實 |
1. 中間市の医療について
(1)市は市立病院を廃止しました。私は、このことは市民の皆さんが不安を抱いていると考えます。市長は「市民の命と健康を守るのは行政の重要な責務である。」と言われています。市民の命と健康を守るために、具体的にどのような方策をされていますか。
(2)また、市として訪問医療を中心とした「診療所」をつくることを提案しますが、市の見解を伺います。
2.学校施設再編について
(1)市は中学校を先行した学校再編の取組を進めています。中間中学校・中間東中学校の敷地を活用するとありますが進捗状況を伺います。
3.訪問介護における駐車場の確保について
(1)訪問介護において、訪問介護事業者は、駐車場の確保に困っているという声を聞きますが、市としてなにか対応策はないのでしょうか。
(2)市営住宅や県営住宅の駐車場に訪問介護用の駐車場を確保し、活用していただくことを提案しますが、市の見解を伺います。
|
植本種實
質問動画<外部リンク> |