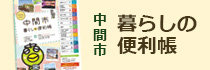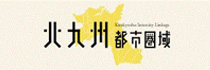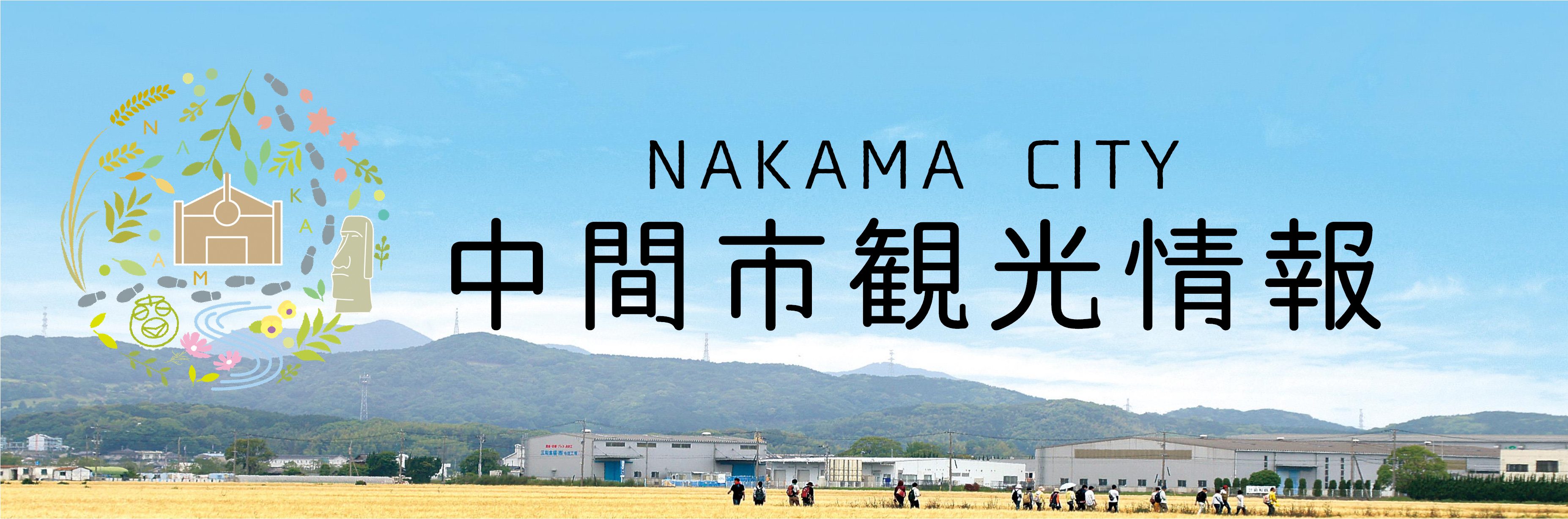本文
後期高齢者医療の保険料と納付方法
後期高齢者医療の保険料
保険料と医療費の負担のしくみ
医療機関などにかかったときの医療費は、被保険者が病院などで支払う窓口負担額と、保険から給付される医療給付費で賄われています。この医療給付費は、約5割を国・県・市町村で、約4割を現役世代の保険料で負担し、残りの約1割を被保険者全員の保険料で負担しています。
保険料の計算方法
保険料は、「被保険者全員が均等に負担(均等割)」と「所得に応じて負担(所得割)」を合計した額です。所得に応じ、公平に保険料をご負担いただきます。
保険料=均等割額+所得割額
令和6・7年度の均等割額は、60,004円です。所得割額は、基礎控除(43万円)を差し引いた後の総所得金額等に11.83%を乗じた額となります。(基礎控除額は合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります)
なお、保険料の1人当たりの上限額は80万円です。
保険料の軽減
所得状況により、均等割が軽減される制度があります。
均等割の軽減
世帯主及び世帯に属する被保険者の軽減対象所得金額の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減対象所得金額とは、給与所得者の場合は「給与収入額」から「給与所得控除額」を差し引いた額、年金受給者の場合は「公的年金等収入額」から「公的年金等控除額」を引き、さらに15万円を引いた額です。
| 世帯主及び世帯に属する被保険者の軽減対象所得金額の合計額 | 均等割の軽減割合 |
|---|---|
|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
7割 |
| 43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
5割 |
| 43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×給与所得者等の数-1) 以下 |
2割 |
(注意)世帯主及び世帯に属する被保険者に、給与所得または公的年金などの所得がある場合に太字の計算式が適用されます。
被扶養者の人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社などの健康保険の被扶養者であった人は、後期高齢者医療制度に加入した後2年を経過するまでの間は、均等割が5割軽減されます。また、所得割の負担はありません。
保険料の納付方法
特別徴収
年金額が18万円以上で、かつ、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1以下の場合の人は、年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、新規加入当初は必ず普通徴収で納める期間があります。一定期間経過後は、自動的に天引き(特別徴収)になりますので手続きは不要です。
なお、年金天引きになる人も、申請により口座振替へ変更することができます。手続きの方法など詳しくは、お問い合わせください。(申請から年金天引きの中止には2~4か月かかります)
普通徴収
特別徴収の対象にならない人は、下記の方法で徴収します。
後期高齢者医療保険料の確定申告について
1年間に納付された後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に社会保険料控除として申告することができます。
なお、確定申告の際には次の書類が必要となります。
普通徴収で納付している方
毎年1月中旬に市役所から郵送される納付証明書
特別徴収で納付している方
日本年金機構等の年金保険者から郵送される源泉徴収票
ただし、源泉徴収票は、老齢年金を受給している方に郵送されます。遺族年金や障害年金などの非課税年金を受給している方には発行されませんので、市役所にお問い合わせください。