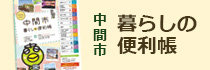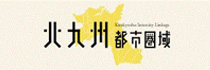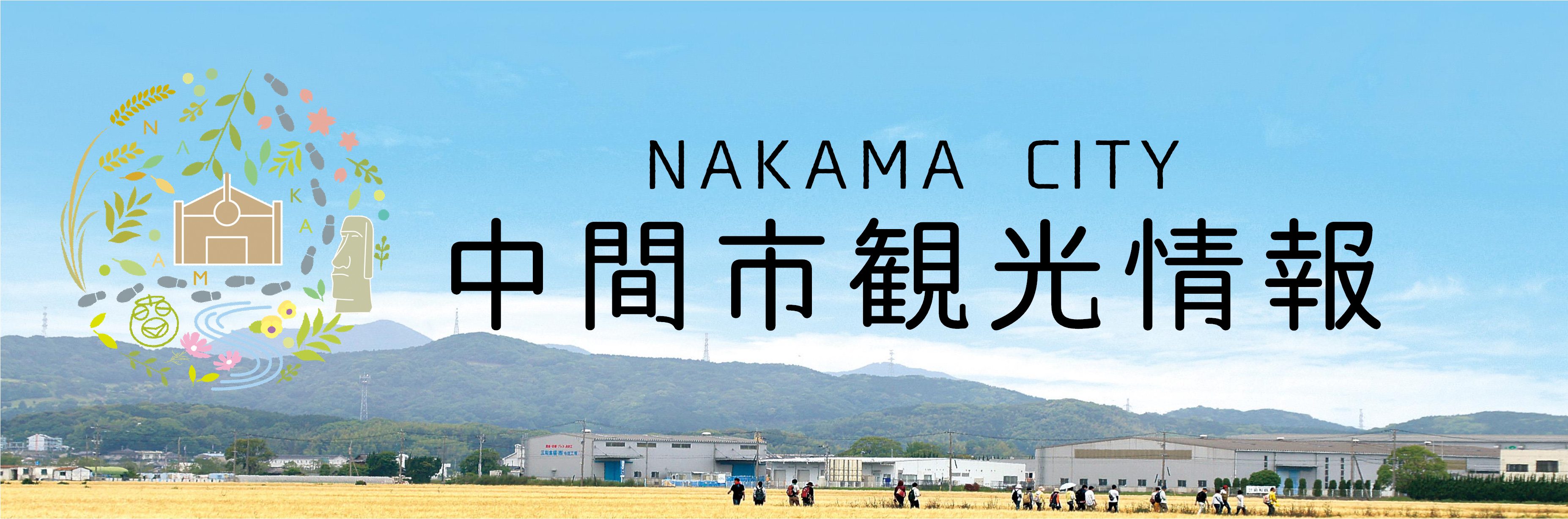本文
フンの片づけは飼い主の責任です
片づけは飼い主が行う・・・最低限のマナーです
散歩中の排泄行為は、他人の私有地や公共の場所を汚してしまうことにつながります。
処理袋や水を携帯し、フンは必ず持ち帰り、水等で流すようにしましょう。
※なるべく自宅の敷地内で済ませるようにし、他人の土地や門扉などですることは避けてください。

フンの放置は中間市の条例違反です!
中間市飼犬条例
第4条1項(3) 飼い主は、道路、公園、広場その他の公共の場所及び他人の土地建物等を汚物で汚し、又は損傷することがないようにすること。
また、刑法上でも公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者⽝のフンを道路や公園に放置する⾏為は、軽犯罪法に違反し、犯罪になります。 軽犯罪法第1条第27号には、次のように定められています。
第1条第27号 「公共の利益に反してみだりにごみ、⿃獣の死体その他の汚物⼜は廃物を棄てた者」は、「これを拘留⼜は科料に処する。」

知っていますか?こんな取り組み
みなさんは、イエローチョーク活動ってご存知ですか?
2016年、京都府宇治市から始まった活動で、道路上に放置された犬のフンの周りを黄色いチョークで囲み、発見した日時を書きこむことで、飼い主に「迷惑を被っている人がいる」という意識を持たせ、フンの放置を減らすことを目的とした取り組みです。



【取組の一例】
中間市でも行われている〇〇チョーク作戦!
実は、他市町村で行われているイエローチョーク作戦をさらに進化させた活動があります。中間市の環境ボランティア団体で始められた運動は、ホワイトチョーク作戦と言います。
チョークで置いて行かれたフンを囲うまでは同じですが、フンを残さず回収し臭いを残さないように、砂等で掃いて清掃をします。活動をされている地域は、児童の通学路になっていることもあり、踏んでしまったり不衛生にならないように環境美化のために現物は取り除くが、啓発も行う活動です。




【市内の取組例】
子ども達には、地域の方の見守りがきっと伝わっていることと思います。
動物を飼うために必要なこと
動物を飼うという事は、命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
散歩中に必要なリードコントロール
犬を散歩することは、犬の健康を保ったり社会性を身につける上でとても大切なお世話のひとつです。
しかし、屋外だからといって、どこでもフン尿をさせてしまうと、他人の私有地や公共の場所を汚してしまうことになります。犬が電柱や私有地に排泄しようとした場合は、飼い主がリードをコントロールして、その場から離れ「この場所はトイレではないよ」という事をしっかり伝えましょう。
もし散歩中にフンや尿をしてしまったら
フンや尿を放置してしまうと、犬を飼っていない人はもちろん、飼っている人にとっても不快です。
そのため、飼犬が散歩中にしてしまったフンや尿は、必ず飼い主が処理をしてください。
尿についても、放置してしまうと、悪臭や汚れの元になるなど、近隣の人にとっては不快なものです。もし、電柱や他人の門扉等にかけてしまった場合は、水や薄めた消毒液をかけて流すようにしてください。
※フンは土に埋めても肥料にはなりません。逆に草木を枯らしてしまうこともあります。埋めたり放置せずに必ず持って帰りましょう。