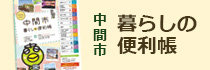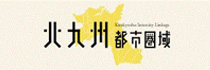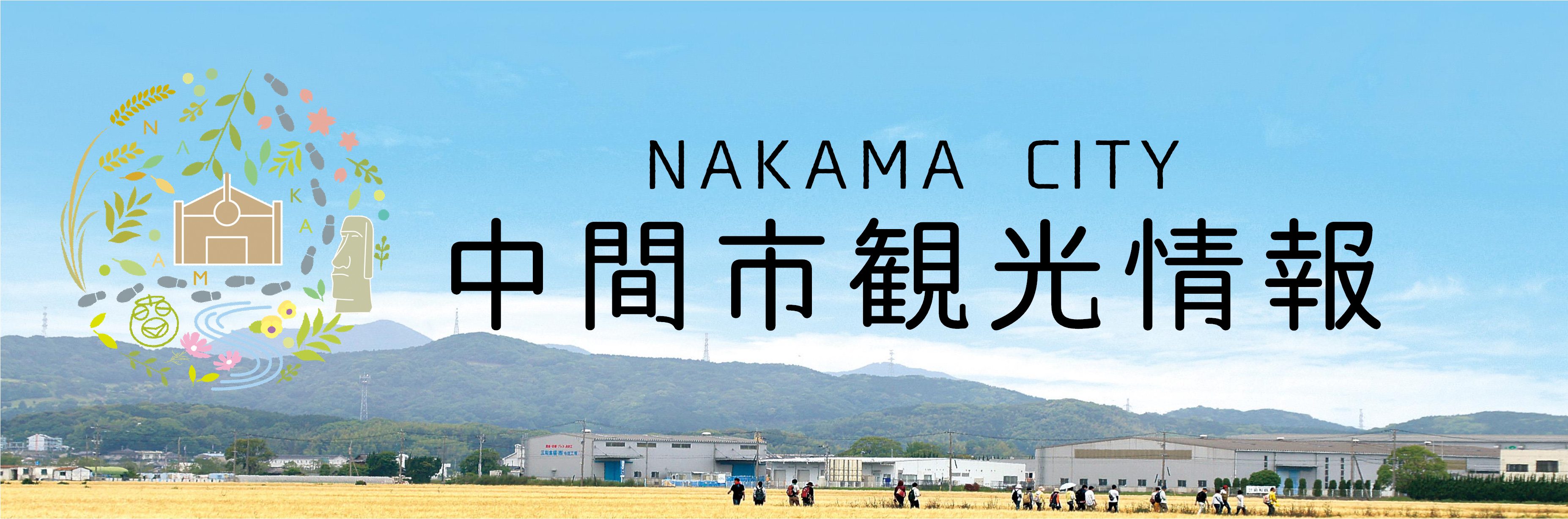本文
令和6年10月から児童手当制度が拡充されました
令和6年10月分(12月支給)から、児童手当の制度が拡充され、令和6年12月10日(火曜日)に
初めて支給が行われました。
世帯の状況により、手続きが必要です。
手続きが必要かどうか、こちらのフローチャート (PDFファイル:149KB)からご確認ください。
(重要)制度改正に伴う申請について 令和7年3月31日(月曜日)必着までは
申請を受け付けます。
支給要件に該当する場合、令和6年10月分以降の拡充分の手当を
支給します。
※令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、
申請した翌月分から支給を開始します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できません。
申請漏れがないようご注意ください。
制度改正の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)」までに延長
- 第3子以降の手当額を月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更※1
- 定期支払通知(ハガキ)の廃止※2
※1 支払日は偶数月の10日となります。(10日が土日・祝日の場合は直前の営業日)
※2 令和6年12月支払から、通帳の記帳などにより、振り込みを確認されてください。
児童手当について
1.児童手当制度の趣旨
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に質するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育し、主に生計の中心となっている保護者に支給されます。
2.手当を受けることができる方(受給対象者)
18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
新制度の児童手当支給額
| 改正後 | 令和6年10月分以降 |
|---|---|
| 支給対象 |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
| 所得制限 | なし |
| 支給月額 |
・3歳未満 第1子・第2子 1万5千円 第3子以降 3万円
・3歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで) 第1子・第2子 1万円 第3子以降 3万円 |
| 第3子以降の要件 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
| 支給時期 |
年6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
1.申請のあった月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
2.第1子、第2子などの数え方は、22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。
進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)が当該子を養育していれば、算定の対象になります。就職等により、自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。
(例:別居している場合)
別居している場合の仕送りについて、その内容が金銭ではなく食料品や生活必需品などの場合であっても、その内容が、この日常生活の全部又は一部を営むために必要で、かつ、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができないと考えられるような場合には、生活費の負担をしていることに該当します。
(例:収入の有無について)
当該子の収入の多寡によって判断されるものではなく、監護相当及び生計費の負担の要件を満たすか否かにより判断されます。
(例)21歳、14歳、7歳、の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額(月額1万円)、
7歳のお子様は第3子以降の月額(月額3万円)が適用されます。(月額4万円)
(注)所得制限・所得上限
令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。
ただし、過去に遡って児童手当が支給される場合、令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。
申請手続き
出生、転入などにより受給資格が生じた場合、「認定請求書」の提出が必要です。
制度改正のご案内について
18歳以下の児童がいる世帯へ、令和6年9月9日(月曜日)に案内を発送しましたので、内容をよくご確認ください。
なお、公募上の情報だけでは対象世帯を正確に把握することはできないため、手続きが必要ない世帯にもお送りしています。
また、対象となる児童の住民票が中間市外にある方や手続きが必要な方でも案内が届かない場合があります。下記の「申請が必要な方」のフローチャートをご確認いただき、申請が必要であれば、ご自身で申請手続きをお願いします。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(注)受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場で手続きを行ってください。
(注)受給資格者が中間市外に住民登録している場合は、住民票のある自治体で申請してください。
(注)受給資格者と支給対象児童のお子様が別居の場合は、申請書の他に別居監護養育申立書の提出が必要です。
申請が必要な方
手続きが必要かどうか、こちらのフローチャート (PDFファイル:149KB)からご確認ください。
各様式および記載例、その他必要な書類については以下のとおりです。
【記入例】児童手当 認定請求書 (PDFファイル:267KB)
・請求者名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードの写し)
【記入例】児童手当 額改定届 (PDFファイル:219KB)
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル:90KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル:102KB)
(4)児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル:50KB)
【記入例】児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル:99KB)
(注)施設・里親の方について
高校生年代のお子様が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、そのお子様については申請が必要です。
施設の場合は施設所在地、里親の方の場合はお住まいの自治体にてお手続きください。
申請先
中間市役所本館1階こども未来課子育て係までご郵送ください。
郵送での手続きのほか、窓口に持参またはご自宅からの電子申請も可能です。
次の1から3のすべてにあてはまる方は、中間市での児童手当の手続きを内閣府のマイナポータルを利用して電子申請で行うことができます。
- 中間市にお住まいの方(住民票上の居住地が中間市内の方)
- 公務員でない方
- フローチャートでD、B、Cに該当する方
上記1から3のすべてに当てはまる方で、電子申請を希望される方は内閣府のマイナポータル(ぴったりサービス)<外部リンク>をご利用ください。
マイナポータル<外部リンク>とは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。
(注意)上記の1から3のすべてにあてはまらない方が中間市に電子申請をされた場合、中間市での手当の受給はできませんので、ご注意ください。
(注意)「監護相当・生計費負担についての確認書」や「児童手当別居監護申立書」などは、電子申請での入力受付を行っておりませんので、様式をダウンロード後、印刷・記入のうえ、添付するか、後日、郵送か窓口でご提出ください。また、申請の内容によっては、その他に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
現況届
令和4年度から児童手当の現況届が原則不要になりました。
毎年6月中に現況届の提出が必要でしたが、令和4年から一部の人を除いて、提出が不要になりました。
ただし、毎年の所得の申告(年末調整等)は必要ですので、お済みでない方は、申告してください。
引き続き現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後継人、施設・里親の受給者
・受給者が児童と別居しており、「別居監護申立書」を提出された方
・父母以外が児童の生計維持者となって受給されている方
・その他状況を確認する必要がある方
上記の要件に該当し、現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に受給者の住所宛てに現況届を送付します。この現況届により受給資格を確認しますので、児童手当を継続して受給するために6月中に必ず提出してください。
なお、現況届の提出が必要な方で提出がない場合は、8月支払い(6月から7月分)以降の手当の支給が一時差止になりますのでご注意ください。
注意事項
・受給者と配偶者の所得を確認した結果、現在の受給者より配偶者の所得が高い場合は、受給者変更をしていただく必要があります。受給者変更となる場合には、新しい受給者の申請、現在の受給者の方の児童手当消滅の手続きが必要となり、別途必要書類があります。
届出内容に変更があったときは手続きが必要です
●児童手当額が変更になるとき
●受給者、または対象児童が他の市区町村へ転出するとき
●受給者や配偶者、対象児童の住所や氏名が変わったとき
●受給者が公務員になったまたは公務員でなくなったとき
●受給者が児童を養育・監護できなくなったとき(拘禁・行方不明など)
●受給者または養育する22歳以下のお子様が婚姻、離婚したとき
●受給者の配偶者と児童が養子縁組をおこなったとき
●振込口座に変更があったとき
●3歳未満の児童を養育する方で、加入する年金が変わったとき
届出にあたって、提出していただく書類が必要な場合がありますの、事前にお問い合わせください。
高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続して養育する場合の手続きについて
令和6年度制度改正により、高校等を卒業した後も、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代まで)については、第3子以降の加算を計算する際の算定対象とすることができるようになりました。
(注)大学生年代の子自身は、児童手当の支給対象外です。
大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)方で、高校等を卒業した子について、卒業後も監護及び生計費の負担をし、第3子加算の算定対象とする場合は、以下の書類の提出が必要です。
(1) 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル:90KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル:150KB)
【記入例】児童手当 額改定請求書・額改定届 (PDFファイル:252KB)
該当する方には中間市から案内を郵送いたしますので、案内が届きましたら期限までに申請してください。
(注)案内は3月上旬頃に発送します。
(注)大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)、かつ、監護・生計費の負担をし、第3子加算の対象とする場合のみ申請が必要です。
(注)進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者が養育していれば申請の対象になります。就職等により、自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
(例:別居している場合)
別居している場合の仕送りについて、その内容が金銭ではなく食料品や生活必需品などの場合であっても、その内容が、子の日常生活の全部又は一部を営むために必要で、かつ、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができないと考えられるような場合には、生活費の負担をしていることに該当します。
(例:収入の有無について)
当該子の収入の多寡によって判断されるものではなく、監護相当及び生計費の負担の要件を満たすか否かにより判断されます。
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを中間市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある人は中間市役所こども未来課までお問い合わせください。