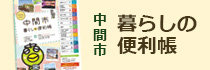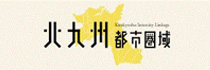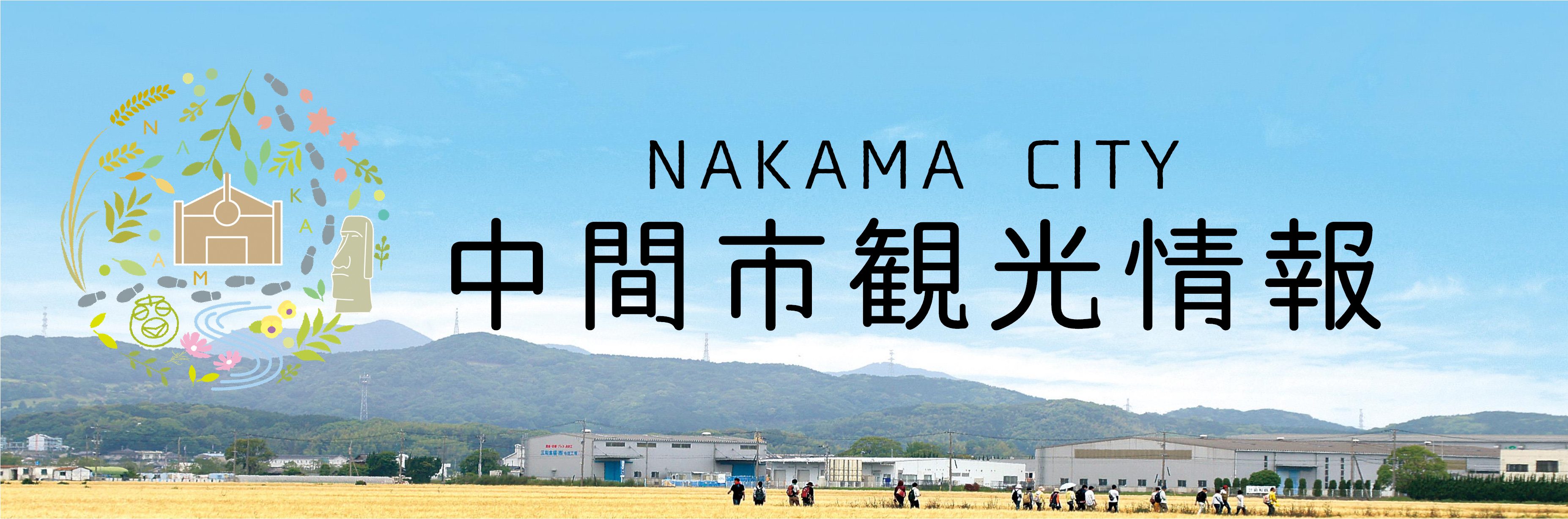本文
子宮頸がん予防接種の期間を延長します
高校1年生相当の方と救済措置(キャッチアップ接種)対象の方へ
厚生労働省での最新の検討状況(2025年1月29日更新)
※今夏以降の大幅な需要増により、Hpvワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
効果と副反応を十分に理解したうえで、接種してください。県内の広域予防接種実施医療機関以外及び県外医療機関での接種は、事前の手続きが必要です。
1.接種対象者
(1).キャッチアップ接種対象者のうち、2022年4月1日~2025年3月31日までにHpvワクチンを1回以上接種した方
(2).2008(平成20)年度生まれの女子で、2022年4月1日~2025年3月31日までにHpvワクチンを1回以上接種した方
2.接種期間
キャッチアップ接種期間(2025年3月31日まで)終了後、1年間
【厚生労働省】ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHpvワクチン<外部リンク>
【中間市】こどもの予防接種
予防接種市内の実施医療機関
事前に医療機関に問い合わせをして、予約して受けましょう。
予防接種を受けることができる医療機関(市内) PDFファイル:78KB)
市外の実施医療機関
遠賀郡内の実施医療機関や福岡県内の予防接種広域化実施医療機関で受けることができます。接種したい医療機関が広域化加入医療機関でない場合は、書類が必要であるため、事前にこども家庭センターへ問い合わせてください。接種後の場合は定期接種と認められず、全額自己負担となります。
ワクチンの効果と副反応
サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHpv16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
シルガード9はHpv16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型のHpv感染を防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
子宮頸がん予防ワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、まだ研究の段階ですが、子宮頸がんを予防する効果を示すデータも出てきています。
ただし、予防接種により、軽い副反応がみられることがあります。また、極めて稀ですが、重い副反応がおこることがあります。予防接種後にみられる反応としては、下記のとおりです。
|
頻度 |
2価ワクチン(Gsk・サーバリックス) |
4価ワクチン(Msd/ガーダシル) |
9価ワクチン(Msd/シルガード9) |
|---|---|---|---|
|
10%以上 |
痒み、接種部位の痛み、赤み・腫れ、腹痛、筋痛・関節痛、頭痛、疲労など |
接種部位の痛み・赤み・腫れ |
接種部位の痛み・腫れ・赤み、頭痛 |
|
1~10%未満 |
じんましん、めまい、発熱など |
接種部位の痒み、頭痛、発熱など |
浮動性めまい、悪心、下痢、発熱、疲労、接種部位の痒み・内出血など |
|
1%未満 |
注射部位の知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 |
下痢、腹痛、手足の痛み、筋骨格硬直、接種部位の硬結・出血・不快感など |
嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、接種部位の出血・血腫・硬結、倦怠感 |
|
頻度不明 |
手足の痛み、失神、リンパ節症など |
疲労感、失神、嘔吐、筋痛・関節痛など |
感覚鈍麻、失神、手足の痛みなど |
(サーバリックス®添付文書(第14版)、ガーダシル®添付文書(第2版)、シルガード®9添付文書(第1版)に基づく)
また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、接種との因果関係を問わず収集しており、定期的に厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)において専門家が分析・評価しています。その中には、稀に重い症状の報告もあり、具体的には以下のとおりとなっています。
|
病気の名前 |
主な症状 |
報告頻度※ |
|---|---|---|
|
アナフィラキシー |
呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー |
約96万接種に1回 |
|
ギラン・バレー症候群 |
両手・足の力の入りにくさなどを症状とする末梢神経の病気 |
約430万接種に1回 |
|
急性散在性脊髄炎 |
頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする能などの神経の病気 |
約430万接種に1回 |
|
複合性局所疼痛症候群 |
外傷をきっかけとして慢性の痛みを生ずる原因不明の病気 |
約860万接種に1回 |
(※2013年3月までの報告のうちワクチンとの関係が否定できないとされた報告頻度)
Hpvワクチンに関する相談先一覧
(1)接種後に症状等があり、相談したいとき
・まずは、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。
・また、福岡県では「Hpvワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を選定しています。
協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。
福岡県内の協力医療機関 [PDFファイル/71KB]<外部リンク>
(2)不安や疑問があるとき、日常生活や学校生活で困ったことがあるとき
・福岡県では、Hpvワクチン接種後に症状が生じた方からの相談窓口を設置しています。
福岡県内の相談窓口 [PDFファイル/89KB]<外部リンク>
(3)Hpvワクチンを含む予防接種、感染症全般についての相談
・厚生労働省においても、Hpvワクチンを含む予防接種や感染症全般の相談を受け付けています。
厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」
電話番号0120-469-283(平日9時~17時(土日、祝日、年末年始は除く))
予防接種健康被害救済制度
・極めてまれですが、予防接種を受けた方に重い健康被害を生じる場合があります。
・Hpvワクチンに限らず、日本で承認されているすべてのワクチンについて、ワクチン接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
・申請に必要な手続については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
厚生労働省 予防接種健康被害救済制度<外部リンク>